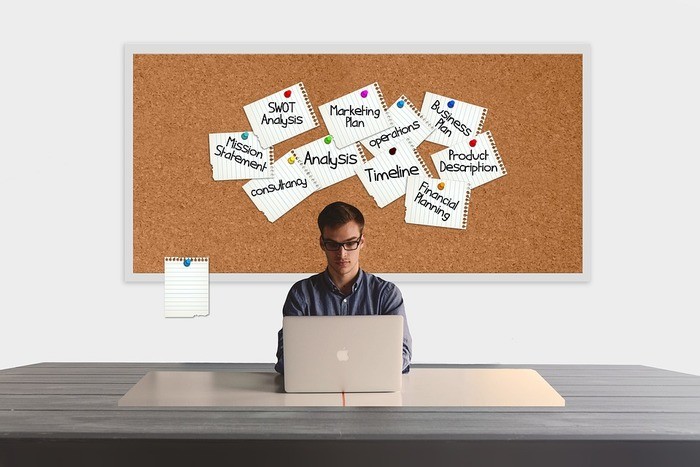

KOSKOSブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
こんにちは!
AO推薦入試専門塾 KOSKOSスタッフです。
今回のテーマは「粗方を決める前に考えておきたいこと」についてお伝えしていきたいと思います。
○「コンセプト」を明確にする
前回、自由記述の作成にあたってその類型をお伝えしましたが、
最も大事なことは「どう書くか」ではなく、「何を書くか」です。
これは自由記述を作成する上で、常に意識しておかなければいけないことといえるでしょう。
逆転合格する人の自由記述は、何を伝えるのか、その目的が明確です。
伝えたいことは1つだけに絞りましょう。
いくつも伝えようとしてはいけません。
伝えたいことが多ければ多いほど、相手は理解できなくなります。
たった一つの伝えたいこととして、「コンセプト」を決める必要があります。
コンセプトとは、直訳すると、「概念、観念」ですが、
ここでの意味として、「一貫したテーマ」と訳すのが適切でしょう。
コンセプトを決めるのには一定の時間がかかりますので、自由記述の一番の難所といえるかもしれません。
「エイヤ!」で決めてしまうと、後々作り直すことになります。
時間のない受験生にとって、それは大きな痛手となりますので、
大幅な時間のロスを避けるためにも、ここは十分に時間をかけましょう。
コンセプトが決まれば、全体の骨格ができ上がったのも同然です。
あとはそれに従って細かい内容を肉付けしていけばいいだけですので、
比較的スムーズに作業が進むはずです。
「自由記述は『コンセプト』で決まる」
逆転合格者は決まってこう話します。
コンセプトの良し悪しが自由記述の質を左右します。
わざわざ、自由記述で伝えるべきことは何なのか?
自由記述の特性を主に意識しながら、十分に時間をかけて考えましょう。

〇縦横自由、2枚続きものもアリ
前述した通り、自由記述は長方形の用紙が2枚です。
縦に使っても、横に使っても構いません。
用紙の向きをどう使うかは、軽視しがちだが、それによってデザインは大きく変わります。
使い方を失敗すると、アンバランスな印象を与えてしまいます。
全体のバランスが悪いと、審査官はパッと見た瞬間、「あれっ?」という違和感を覚えます。
そして、最終的には不合格の烙印を押されてしまうのです。
一人ひとり見せ方、内容は異なるので、どれがベストということはありません。
使用する写真や図の形や大きさなど、様々な条件を考慮して決める必要があります。
図や写真の形、文章の長さなどを総合的に判断しましょう。
事実、KOSKOSの塾生も縦横自由に使っています。
これまで比較的多かったのは、用紙を縦に使って、それぞれ1枚もので作成するパターンです。
ただし、それも特段に多かったというわけではありません。
「2枚続きもの」として見せるのか、別々のものとして見せるのか、それも判断によります。
2枚続きものとは、複数枚のカードを組み合わせて1つの絵になるようなデザインということです。2枚で組み合わせて見せれば、その分、壮大な作品になります。
その際、注意点は次の2点です。
①つなぎ目を計算すること。
②コンセプトを貫くこと。
①について、つなぎ目が段違いになってしまうと、一気にチープな印象を与えてしまいます。
実際に作成したら、つなぎ目がきちんと合っているか確認することが必須です。
②について、1枚目と2枚目でコンセプトが異なるというのは問題外です。
そうであるならば、わざわざ2枚続きものにする必要性はありません。
ストーリーの繋がりを意識することでスムーズに2枚目も見てもらえるでしょう。
作成に取り掛かる段階で、どのように用紙を使うか決めていないと、
後で修正するのにかなりの時間がかかります。
粗方を決める際に、用紙の向き、使い方もしっかり検討しておきましょう。

今回は「粗方を決める前に考えておきたいこと」についてお伝えしてきました。
いかがだったでしょうか?
もし、今回の記事を読んで質問や相談がある方は、ぜひKOSKOS公式ホームページまでお問合せください。
また、KOSKOSではAO入試、推薦入試受験生、保護者を対象に無料個別相談を実施しています。
KOSKOSの認定講師がマンツーマンであなたの質問、相談にお答えします。
次回は「自由記述はどのように作成するべき?」についてお伝えしていきたいと思います。
どうぞ、ご期待ください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
質問、相談大歓迎!
