
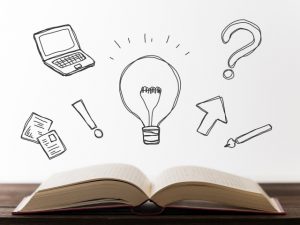
KOSKOSブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
こんにちは!
AO推薦入試専門塾 KOSKOSスタッフです。
今回のテーマは「”入学前課題”を侮るな!」についてお伝えしていきたいと思います。
いざ、合格すると、「大学の講義についていけるか心配……」という人がいます。
正規のルートで受験をして、大学から合格をもらっているということは、
「あなたはウチの大学で学ぶだけの下地はありますよ」といってもらっているのと同じことです。
それにAO入試入学者に対しては、
ほとんどの大学で「入学前課題」が出され、継続的にフォローしてもらえる仕組みになっています。
内容は大学によって様々ですが、基礎学力を鍛えるワークから、課題図書レポートなど多岐にわたります。
このタイミングで、一般入試受験生と比べて、不足しがちな基礎学力や一般教養の知識を補うことができます。
合格した反動で、高校卒業まで「遊び一辺倒」になってしまえば、入試時よりも学力が下がるなんてこともあり得るでしょう。
「入学前課題はやらないと、何か損をしますか?」などと情けない質問をしてくる人もいます。
そこでもし、誰かが「何も損はしないよ」といったら、手を抜くつもりなのでしょうか?
入学前課題にも手を抜かないでほしいという理由は三点あります。
第一に、一年次の奨学金の選考対象になるからです。
二年次以降は学部の成績や研究業績で評価しますが、一年次には参考にできる判断材料がありません。
そこで、高校在籍時の成績に加え、入学前課題の出来を加味するのです。
第二に、所属したいゼミの評価対象になるから。
入学前課題の内容以上に、「よく頑張っているな」という印象点で大きく影響してくるでしょう。
第三に、合格を出してくれた審査官に対して裏切り行為になるから。
入試選考の時に、審査官の票が割れる場合もあります。
その時に、あなたを見込んで「私が責任を持って指導する」と言ってくれた審査官がいたらどうでしょうか?
あなたはそうした人に対して、平然と顔向けできますか?
入学前課題を活用して、新生活のスタートダッシュを成功しましょう。

〇「合格後」に志望理由書を書き直す。
入学後にやりたいことが変わるのは、自然なことです。
高校生の時に希望していたことが、そのまま大人になっても変わらない人のほうが珍しいでしょう。
変わるということは、成長しているということです。
変化が必ずしも「良い変化」だとは限らないという人もいますが、その意見には反対です。
長い目で見れば、一見「悪い変化」と思える事も結果的にそれがきっかけとなり今以上の良い状態に導いてくれることがほとんどです。
人は生きている以上、必ず変化します。
その変化は一見、過去のあるポイントから見れば下がっているように見えても、
長期的なスパンで見れば、必ず上がっているのです。
つまり、人はただ生きているだけでも成長しているということです。
問題はその「成長スピード」です。
だからこそ、志の高い合格者は受かった後に志望理由書を書き直すのです。
彼らは、前述したように志望理由書を「人生の羅針盤」と捉え、
日々、アップデートしていくものだという認識を持っています。
彼らにとって、志望理由書とは、決して「受験のために嫌々書かされたもの」ではないのです。
入試すら突破していないあなたにとっては、随分と崇高な話に聞こえるかもしれません。
果たして、自分もそのような立派な合格者になれるのだろうかと、不安になっても仕方ありません。
ほとんどの塾生が「こんなに長い文章書けません」「何度も、何度も書き直して心が折れそうです」と弱音を吐いていたものです。
志望理由書を書くという行為をもっと気軽に考えてみましょう。
また、そもそも死ぬまで完成形になることはないのですから、
一発で上手な文章に仕上げようなどと意気込む必要はありません。
考え方を変えて、志望理由書を一生付き合っていくパートナーとして一緒に寄り添っていきましょう。
考え方、心の持ちようであなたの行動は180度変ります。

さて、今回は「”入学前課題”を侮るな!」についてお伝えしてきました。
いかがだったでしょうか?
もし、今回の記事を読んで質問や相談がある方は、ぜひKOSKOS公式ホームページまでお問合せください。
また、KOSKOSではAO入試、推薦入試受験生、保護者を対象に無料個別相談を実施しています。
KOSKOSの認定講師がマンツーマンであなたの質問、相談にお答えします。
次回は「AO入試で身につけたスキルを研鑽し続ける!」についてお伝えしていきたいと思います。
どうぞ、ご期待ください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
質問、相談大歓迎!
