
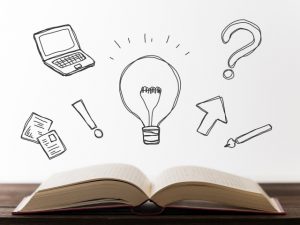
KOSKOSブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
こんにちは!
AO推薦入試専門塾 KOSKOSスタッフです。
今回のテーマは「過去の活動は”点より線”が大事」についてお伝えしていきたいと思います。
どれだけ高い目標を掲げても、そのために行動したことがなければ説得力はありません
単なる思いつきだと思われても仕方がないでしょう。
過去の活動について触れることで、あなたの志が本物であることを示すことができます。
もちろん、志望理由書にこれまでのすべての活動を長々と書くことはできません。
代表的なものを取捨選択する必要があります。
では、どのような視点で優先的に書くべきものを選別するのでしょうか?
その一つの基準が「点より線」です。
点とは、1回限りの活動のこと。
線とは、一定期間にわたって継続的に行ってきた活動を指します。
つまり、単発のイベント参加よりも、
3年間の委員会活動のほうが原則的には、評価の対象になるということです。
「原則的には」としたのは、無論、1回限りのスピーチコンテストだったとしても、
それまでの練習の過程は無視できないからです。
あくまでもケースバイケースであることは言うまでもありませんが、考えてもみましょう。
「将来はトリマーになりたいです。これまで動物は飼ったことがありません。」
「将来はトリマーになりたいです。犬を10年間、育ててきました。」
このような二人の受験生がいたとして、あなたが審査官だったら、どちらの受験生を信用するでしょうか?
一目瞭然、後者でしょう。
まさに「継続は力なり」です。
説得力を持たせる意味では、あなたが「熱意」を持って「長い月日」を費やしてきた活動に勝るものはありません。

〇「新規性」がなければ、優れた研究にはならない。
研究には必ず「新規性」が求められます。
大学院入試ともなれば、研究の新規性は極めて大きなウェイトを占めます。
新規性が多ければ多いほどユニークな研究と見なされます。
高校卒業前後の受験生が受ける大学学部レベルの入試で、多くの新しさを求めるのは少々酷かもしれませんが、それでも、少なくとも一つは「新しさ」がほしいところです。
「この研究、もう他の人がやっているよ」と言われてしまったらおしまいだと思い、
受験生はインパクトのある新規性をいかにアピールするかに苦心します。
新規性と聞いて、「ノーベル賞をとれるような研究」などと勝手にハードルの高いものを想像してしまう人がいますが、心配は無用です。
新規性の打ち出し方として、ここでは三つのヒントを紹介しましょう。
①「手法」を変えてみる
「どの学問から研究するか」といったアプローチを変えることで、これまでにない研究にすることができます。
②「対象」を変えてみる
手法はそのままであっても、それを適用する対象が新しければ、それは十分に新規性のある研究といえます。
③「解釈」を変えてみる
解釈を変えて、新しい見解を導き出す方法ですが、これは社会科学や人文科学の研究に多いです。
もちろん、新規性の打ち出し方はこれだけではありませんが、
前述したヒントを参考にすれば、自分の研究の新規性を作りやすくなるでしょう。
他の研究との違いを出すことはさほど難しいことではありません。
研究に没頭してしまうと、視野が狭くなりがちです。
気張れば気張るほど創造力は働かなくなります。
リラックスして考えてみると、新たな視点が浮かび上がってくる確率が高くなります。

さて、今回は「過去の活動は”点より線”が大事」についてお伝えしてきました。
いかがだったでしょうか?
もし、今回の記事を読んで質問や相談がある方は、ぜひKOSKOS公式ホームページまでお問合せください。
また、KOSKOSではAO入試、推薦入試受験生、保護者を対象に無料個別相談を実施しています。
KOSKOSの認定講師がマンツーマンであなたの質問、相談にお答えします。
次回は「”効率性”だけを追求してはいけない」についてお伝えしていきたいと思います。
どうぞ、ご期待ください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
質問、相談大歓迎!
