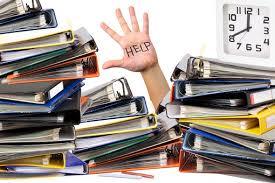
KOSKOSブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
こんにちは!
AO推薦入試専門塾 KOSKOSスタッフです。
今回のテーマは、前回に引き続き…
「勝つ!小論文の「切り抜け方」~実践編②~」についてお伝えしていきたいと思います。

◆原稿用紙が半分も埋まらない!
「書くことが思い浮かばなくて、半分も原稿用紙が埋まらない」
こちらも「小論文あるある」です。
特に1,000字以上の小論文になると、「400〜500字を埋めるのがやっと……」という受験生も出てきます。
残りの空白を見てゲンナリし、戦意喪失してしまう受験生も少なくないでしょう。
その時点で試験終了です。
原稿用紙を埋めようと躍起になり、設問とは関係のない内容や中身のない内容を延々と書き続ける……。
そんなことをして原稿用紙を埋めても、逆効果です。
では、どのようにすれば、原稿用紙を埋めていくことができるのでしょうか?
ここでは次の4つの方法を紹介したいと思います。
対処法① 「例えば」「具体的に」
対処法② 実体験を盛り込む
対処法③ たしかに〜しかし〜
対処法④ 第三者のお墨付き
これらは、ただ単に文字数を稼ぐための「その場しのぎ」ではなく、説得力を持たせるためにも有効です。
それでは、一つひとつ詳細をお伝えしていきます。
対処法①「例えば」「具体的に」
原稿用紙を埋めるための対処法1つ目は、「例えば」「具体的に」です。
「例を挙げて説明してください」
「もっと具体的に書きましょう」
あなたも添削を受けた際、このように指摘されたことがあるのではないでしょうか。
採点官は受験生の小論文にサッと目を通して、次のキーワードがないか瞬時にチェックしています。
「例えば」
「具体的に」
これらは魔法のキーワードです。
例を挙げることで採点官も内容をイメージしやすくなります。
「抽象的→具体的」の形は勝論文のテッパンです。
また、具体的に言うことで詳しく説明できるのです。
内容を掘り下げれば、当然ですが、文字数も稼げます。
1つの例で3行程度はすぐに増やすことができます。
仮に3つの理由でそれぞれに例を入れたとしたら、それだけで10行程度はボリュームアップできる計算になります。
勝論文には必ずと言って良いほど、「例えば」「具体的には」といったキーワードが入っています。
対処法②実体験を盛り込む
原稿用紙を埋めるための対処法2つ目は、「実体験を盛り込む」です。
「誰かから聞いた話」
「自分が体験した話」
どちらの方がより説得力があるでしょうか?
答えはもちろん、「後者」です。
情報は次のように分類することができます。
□一次情報
□二次情報
□三次情報
一次情報とは、自分が実際に目で見て、体験した情報のことです。
二次情報とは、自分が当事者から聞いた情報のことです。
三次情報とは、テレビや新聞などから得た情報のことです。
これらの情報の中で最も説得力が高いのは一次情報ということになります。
説得力という意味では、一次情報に勝るものはありません。
注意点として、自分だけがわかる実体験(内輪ネタ)は NGです。
勝論文では決まって一次情報が随所に盛り込まれています。
論を展開するにあたって、自分自身の体験から語れることはないか、思い返してみてください。
対処法③たしかに〜しかし〜
原稿用紙を埋めるための対処法3つ目は、「たしかに〜しかし〜」です。
小論文で課せられるようなテーマでは、「100:0」で賛成か反対かにわかれることはありません。
賛否両論あるはずです。
そこで、考えるべきは自分とは異なる意見にも必ず論理があるということです。
世の中には多様な人がいるため、それぞれの視点で違ったものの見方が生まれます。
そのことを踏まえて、独りよがりの意見ではないということが伝えられれば、あなたの小論文により深みが増します。
その技術が、「たしかに〜しかし〜」なのです。
自分の意見を述べた後に、「たしかに〜」と自分の意見とは反対の人の意見も一理あることを認めます。
そうすることで、反対意見を持った人に対しても一定の理解を示す余裕を見せることができます。
勝論文にはその余裕が漂っています。
□視野の広さ
□考えの深さ
□著者の度量
「たしかに〜しかし〜」を使って、このような器の大きさをチラつかせましょう。
ここで、賛成・反対メモが活きてきます。
両方の意見を考えているので、自分とは反対の意見も書き出しているはずです。
そのうちのどれか一つを使いましょう。
注意点として、「しかし〜たしかに〜」などと誤った使い方をすると、途中で意見がブレてしまう恐れがあります。
論理展開を疑われてしまいますので、気をつけましょう。
対処法④第三者のお墨付き
原稿用紙を埋めるための対処法4つ目は、「第三者のお墨付き」です。
信頼できる第三者の声があると、読み手は信じ込みやすくなります。
ホームページなどでも「推薦者の声」が掲載されていることがあるでしょう。
人は権威に弱い生き物です。
心理的効果は大きいです。
当然、権威づけの意味で盛り込むわけですから、誰でも良いわけではありません。
□専門家
□第一人者
□大学教員
□研究者
□公人
□有識者
このような第三者の声を付け加えることで、小論文の説得力がグンと高まります。
「○○大学の●●教授もこう主張している」
「△△省の▲▲調査官も次のように分析している」
このようにして、あなたの主張にグッと厚みを持たせるわけです。
事前に情報をインプットしておく必要はあります(人名、肩書きなどの誤表記は減点対象です)が、
うまく第三者のお墨付きを活用することができれば効果は絶大です。

もし、今回の記事を読んで質問や相談がある方は、ぜひKOSKOS公式ホームページまでお問合せください。
また、KOSKOSではAO入試、推薦入試受験生、保護者を対象に無料個別相談を実施しています。
KOSKOSの認定講師がマンツーマンであなたの質問、相談にお答えします。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
質問、相談大歓迎!
