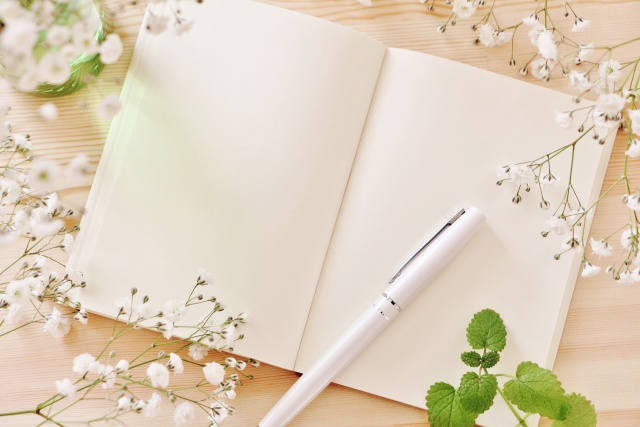

KOSKOSブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
こんにちは!
AO推薦入試専門塾 KOSKOSスタッフです。
今回のテーマは「読み手に好印象を与える小論文の書き方」についてお伝えしていきたいと思います。
○「だ・である」調か、「です・ます」調か?
志望理由書は「文体」一つで、審査官に与える印象がガラッと変わります。
文体には「敬体」と「常体」の2種類があり、いずれかに統一することは基本中の基本です。
その上で、「です・ます調」にするのか、「だ・である調」にするのか、
どちらを選択するかはあなたの判断によります。
KOSKOSでは、受験する学部によって文体を変えるように指導しています。
伝わる文章を書くためには、「この文章を読むのは誰か」を考えることが大事です。
「大工には大工の言葉を使え」
これはかの有名な哲学者、ソクラテスの言葉です。
つまり、相手の立場なって伝えるということです。
「だ・である」調は、カチッとした印象を与えます。
論文のような固い文章がマッチする学問領域、
例えば、「法学系」や「理工学系」などには適しているでしょう。
慶應SFCの場合、総合政策学部、環境情報学部を受験する人は、
「だ・である」調で書く人が少なくありません。
また、文字数も敬体に比べて抑えることができます。
一方、「です・ます」調は、優しい印象を与えることができます。
看護医療学部を受験する人は「です・ます」調で書く人の方が圧倒的に多いです。
というのも、看護医療学部のアドミッション・ポリシーでは、次のような人を求めているからです。
「人の健康と生命、看護への関心をもち、他者の苦痛や悩みを理解しようとする」
そのため、「です・ます」調で書いた方が、よりイメージに近くなると考えたのでしょう。
いずれにせよ、前述したように、読み手を意識して書くことが、志望理由書作成の極意といえます。
志望理由書の内容が完成したら、両方の文体で書いてみて、見比べてみるとよいでしょう。
その違いをはっきりと認識できるはずです。
どちらの方がより研究分野のイメージに合っているのか。
どちらの方がよりあなたらしさを発揮できるのか。
その基準で選択しましょう。
繰り返しますが、重要なことは、文体をマニュアル通りに変えることではなく、
「誰が読むのか」という相手を意識して文章を書くことです。
読み手を思いながら書くということは、書類選考全般を通じて忘れてはならない最も大切なことです。
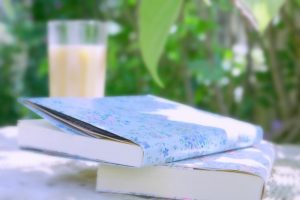
○「ストーリー」に一貫性を持たせる
読ませる文章には必ず「ストーリー」があります。
ここでいうストーリーとは、志望理由書を展開する筋道のことです。
ストーリーがあるから読み手は感情移入できるのです。
ストーリーの良し悪しで志望理由書は決まるといっても過言ではありません。
KOSKOSでは、志望理由書を作成する際、
特にストーリーの「つながり」を意識するように指導しています。
志望理由書でハネられる受験生の多くはこのつながりが不自然なのです。
唐突に過去の活動内容が出てきたり、志望動機と入学後の研究で矛盾が生じたりしがちです。
つまり、一貫性が見えないのです。
□過去
□現在
□未来
志望理由書はこの3つの時系列に沿って、展開されるのが一般的です。
それぞれを整理したら、ストーリーとしてつなげる必要があります。
各パートでブツ切りにならないように気をつけなければなりません。
この作業はそう単純ではありません。
なぜなら、いくつもの切り口があるからです。
切り口は一人ひとり違いますので、「模範解答」があるわけではありません。
「うまい切り口を見つけるコツはありませんか?」
そう質問しにくる受験生がいますが、 はっきりいって、愚問です。
「コツなどない」のです。
そんな質問をしている時間があったら、1つでも多くのパターンを考えてみるべきです。
切り口のうまさは試したパターンの数に比例するものです。

今回は「読み手に好印象を与える小論文の書き方」についてお伝えしてきました。
いかがだったでしょうか?
もし、今回の記事を読んで質問や相談がある方は、ぜひKOSKOS公式ホームページまでお問合せください。
また、KOSKOSではAO入試、推薦入試受験生、保護者を対象に無料個別相談を実施しています。
KOSKOSの認定講師がマンツーマンであなたの質問、相談にお答えします。
次回は「慶応SFCの志望理由書で注意したいこと」についてお伝えしていきたいと思います。
どうぞ、ご期待ください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
質問、相談大歓迎!
