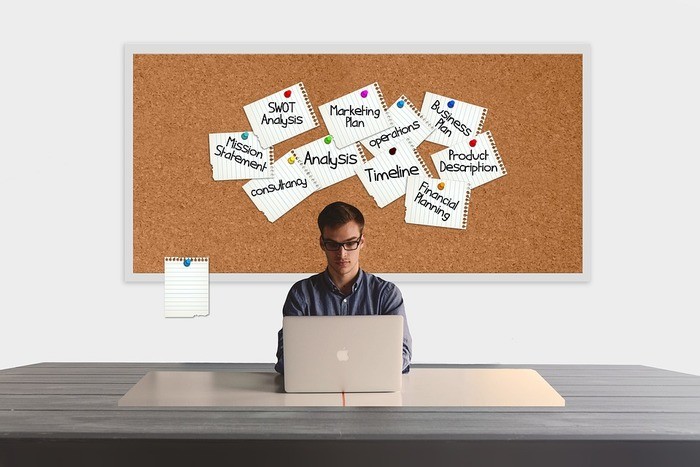
KOSKOSブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
こんにちは!
AO推薦入試専門塾 KOSKOSスタッフです。
今回のテーマは「”勝つ”小論文の考え方」についてお伝えしていきたいと思います。

◆多くの受験生が小論文を誤解している
「敵を知らずして勝利なし」
ビジネス、スポーツ、研究など様々な分野で使われている言葉です。
このことは小論文にも当てはまります。
私は毎年、受験生から小論文に関する様々な悩み相談を受けます。
その度に、多くの受験生が小論文に対して間違った考え方をしていることに驚かされます。
「小論文には答えがない」
「オリジナリティーが大事」
「本音を書かないとダメ」
このような誤解をしている受験生がどれだけ多いことか……。
さて、あなたは小論文に対して正しい理解をしていると自信を持って言えるでしょうか?
ひょっとしたら、あなたもこのように感じているかもしれません。
誤解したままでは一向に小論文で勝つことはできません。
まずはこうした誤解を一つひとつ正していく必要があります。
そこで、前述したような受験生が陥りがちな7つの誤解を紹介し、
小論文で勝つための考え方、姿勢を身につけていただきます。
きっと今までの喉のつかえがスッと取れるはずです。

誤解①「小論文=作文」だと思っている
早速ですが、「小論文」とは何でしょうか?
これから小論文を学ぼうというのに、この問いに的確に答えることのできる受験生は実に少ないです。
まずは小論文の定義について理解していなければ勝負にすらなりません。
中には、小学生のときに書いた作文と混同している人がいます。
「小論文=作文」だと誤解しているのです。
小論文と作文は似て非なるもの。
具体的な違いはこうです。
小論文では、あなたの「論」を述べます。
一方で、作文では、あなたの「感想」を述べます。
両者の決定的な違いは、「論」が必須か否かです。
「そもそも、論とは何かがわからない」という声が聞こえてきそうです。
一言で説明すると、次のように言えます。
「意見+理由」
これが論です。
つまり、小論文とは、「あなたの『意見』と『理由』をセットで答える文章のこと」と定義できます。
作文に論が含まれていなくても、マイナスにはなりませんが、小論文には論が不可欠となります。
勝つ小論文(勝論文)を書く人は、決まって説得力のある論を展開しています。

誤解②「小論文=速記試験」だと思っている
小論文と聞いて、速記の練習をしようとする人がいますが、そんなことはまったくの的外れです。
確かに、小論文の試験本番で時間切れになってしまう受験生は少なくありません。
ですが、それは文字を書くスピードが遅いことが原因ではありません。
一般的な小論文の試験時間、文字数は、60分で800〜1,000字が標準です。
試しに、60分間で題材はなんでも良いので800〜1,000字程度の文章を書き写してみてください。
おそらく15〜20分程度で落ち着いて書き上げることができるはずです。
留学生のように、日本語に慣れていないというのであれば話は別ですが、
日本人であればいくら文字を書くのが遅い人でも十分に書き上げられる量なのです。
これはつまり、小論文は速記の試験ではないということです。
文字を早く書けるに越したことはありませんが、
一般的なスピードで書くことができれば、特段早く書けなくても良いのです。
では、小論文で求められている能力は一体、どのようなものなのでしょうか?
それはズバリ、「構成力」です。
構成力とは、「何をどの順番で伝えるか」ということを考える力です。
小論文で勝つ人は、試験が始まった瞬間から、いきなり書き出すようなことはしません。
それどころか、20〜30分くらい手を止めてじっくりと思考します。
何をどう書くかをまず考え、構成が決まったところで、やっと鉛筆を持つのです。
小論文について誤解している人は、「早く書かなければ……」と試験開始の合図とともに焦って書き出します。
小論文で勝つ人は、じっくり考えてから書き出しても間に合うことを知っているので余裕があります。
むしろ、そうすることで説得力の高い小論文を書くことができるとわかっているのです。
さらに、そのようにしてしっかりと構成が練られていれば、
何度も書き直す必要もなくなり、結果として早く書き上げることができます。

誤解③「小論文は答えのない試験」だと思っている
「小論文が難しいと言われる最大の理由は、答えがないからだ」という人がいます。
果たして、本当にそうでしょうか?
実は、これも間違いです。
確かに、合格者が一様に同じ答案になるわけではありません。
しかし、だからと言って、それは答えがないということにはなりません。
小論文には確実に「答え」があります。
出題者があなたに書いてほしいと思っていることがあるのです。
出題者には必ず意図があります。
意図とは、出題者の真の狙いのことです。
設問の意図を汲むことが小論文では大事であり、的外れなことを書いていては、
得点には結びつかないどころか、大きく減点されてしまいます。
求められている意図を外したままでは、文章を書き進めれば進めるほど、小論文突破は遠のきます。
この意図さえ把握できれば、何を書けば良いのかわかったも同然です。
では、どうすれば意図をつかむことができるのでしょうか?
意図は設問に隠されています。
熟読すれば、ヒントが見えてくるはずです。
□問いに答えていない
□論点がズレている
これらは小論文で落とされる典型パターンだと心得ておきましょう。

誤解④合格点ではなく、「満点」を目指している
小論文は覚える知識が少なく、大変コスパの良い試験科目と言えます。
例えば、大学入試で言えば、日本史や世界史を選択すれば、教科書を丸々一冊覚えなければいけません。
このような暗記科目でなくとも、数学であれば最低限度の公式や出題パターンを詰め込む必要があるでしょう。
その意味で小論文は覚えることがごくわずかです。
時事問題は直前で多少なりとも詰め込む必要がありますが、それでも他の科目と比べて、圧倒的に少ないです。
合格点を取るためのポイントは、「ミス減らすこと」です。
その理由は小論文の採点方式になります。
あらゆる試験の採点方式は、「加点方式」「減点方式」に大別されます。
加点方式とは、良い点を見つけて点を付け足していく採点方式です。
例えば、面接は加点方式で採点されます。
「他の受験生よりも優れた回答をしたからプラス点」といったように採点されます。
減点方式とは、悪い点を見つけて点を引いていく採点方式です。
つまり、「誤字脱字があるのでマイナス点、原稿用紙の使い方が間違っているのでマイナス点、論理が矛盾しているのでマイナス点……」といったように採点されます。
小論文は後者で示した減点方式で採点されます。
加えて、小論文の特徴として満点を狙うことは極めて難しいです。
その理由は、小論文では完璧な答案(矛盾点のない論)を書くことは至難の技だからです。
中には、「どうせ受験するなら満点狙い」という目標の高い受験生もいますが、目的を忘れてはいけません。
あなたの目的は小論文で満点を取ることですか?
それとも、最終合格を勝ち取ることですか?
もし、小論文突破は通過点であるなら、満点ではなく、
「合格点」を確実に取れるように目標を立ててほしいと思います。
それでは、この続きはまた明日お話させて頂きます。

もし、今回の記事を読んで質問や相談がある方は、ぜひKOSKOS公式ホームページまでお問合せください。
また、KOSKOSではAO入試、推薦入試受験生、保護者を対象に無料個別相談を実施しています。
KOSKOSの認定講師がマンツーマンであなたの質問、相談にお答えします。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
質問、相談大歓迎!
