
KOSKOSブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
こんにちは!
AO推薦入試専門塾 KOSKOSスタッフです。
今回のテーマは昨日に引き続き、「小論文の”作法”とは?」についてお伝えしていきたいと思います。

作法⑥ひらがなと漢字は「8:2」が理想的
明文はうまい具合にひらがなと漢字の分量が調整されています。
漢字とひらがなで適度なバランスが保たれていると、読みやすい上に、見た目にも美しいです。
「明後日の新入生歓迎会では、各学部の集合場所に目印が無い所もある為、場合に依っては定刻通りに集まる事が出来ない人が出ると思う」
このように漢字だらけの文章が書かれていたらどうでしょう?
読みづらいですよね。
また、逆にひらがなだらけの文章もすこぶる読みにくいです。
「あさってのしんにゅうせいかんげいかいでは、かくがくぶのしゅうごうばしょにめじるしがないところもあるため、ばあいによってはていこくどおりにあつまることができないひとがでるとおもう」
これではいずれも、相手は読む気になりません。
どれくらいがちょうど良いのかというと、「8:2」が理想的です。
せめて、次の文章くらいには漢字を減らす必要があるでしょう。
「明後日の新入生歓迎会では、各学部の集合場所に目印がないところもあるため、場合によっては定刻通りに集まることができない人がでると思う」
このくらいの比率であれば、相手も読みやすいと思います。
もちろん、絶対にその比率でなければならないということではありません。
すべての文章がキレイに8:2で書けるはずもないので、あくまでも目安として捉えてください。
「少し漢字が多いかな」と感じたら、意図的にひらがなにしてみましょう。

作法⑦基本は「だ・である」調で書く
文体には、次の2種類があります。
「常体」
「敬体」
前者は「だ・である調」、後者は「です・ます調」と呼ばれるものです。
では、小論文の場合、どちらで書くのが正しいのでしょうか?
答えは「どちらも正解」です。
大事なことは、小論文全体を通じて文体を揃えることです。
前半は「です・ます調」で書いていたのに、後半から「だ・である調」に変わるなどしたら、減点対象となります。
意識的に文体を変える受験生はいないでしょうが、部分的に「うっかり文体を混在させてしまった」というミスをしてしまう受験生は多いので注意してください。
ちなみに、一般的には「だ・である調」で書くことがより好ましいとされています。
カチッとした印象を与え、論文らしく見えるからでしょう。
「だ・である調」で断言することで、自信も伝わります。
その上で、私は相手によって文体を変えることを推奨しています。
仮に、大学入試であれば、学部によって文体を変えるのです。
例えば、看護医療学部のような「優しさ」「丁寧さ」が求められる学部では、あえて「です・ます調」で書くことによって、それらの能力、適性をアピールできるでしょう。
法学部のような論理的な思考が強く求められる学部では、やはり、「だ・である調」で書いた方が採点官の印象は良いのではないかと思います。
文章を書くときの基本である「誰が読むか」を意識して文体を検討してみてください。
 作法⑧カッコを適切に使い分ける
作法⑧カッコを適切に使い分ける
あなたは適当にカッコを使っていませんか?
カッコにはいくつかの種類がありますが、小論文で使うカッコは基本的に次の2種類です。
①は「カギカッコ」と言います。
文章では会話を表現するために使われます。
〔例〕小論文について誤解している人は、「早く書かなければ……」と試験開始の合図とともに焦って書き出します。
また、引用を示す際や、強調する際にも登場します。
〔例〕実業家、ジョン・ロックフェラーは言いました。「成功の秘訣は、当たり前のことを特別上手にすることだ」と。
〔例〕合格点を取るためのポイントは、「ミス減らすこと」です。
文章中で使われる頻度は高いため、あなたも慣れ親しんでいるカッコだと思います。
②は「二重カギカッコ」と言います。
こちらはカギカッコの中で使われます。
〔例〕つまり、小論文とは、「あなたの『意見』と『理由』をセットで答える文章のこと」と定義できます。
また、タイトル名、作品名を表記する際にも用いられます。
〔例〕小杉樹彦著『減点されない!勝論文』
カッコの使い方一つでも減点になりかねませんので、適切に使い分けましょう。

作法⑨制限字数を守る
字数を守るのは小論文の大原則です。
これが守れないようでは、最悪の場合、一発アウトになってしまう恐れもあります。
これまでの努力が一瞬にして水の泡となってしまいますので、十分に気をつけなければいけません。
ひょっとしたら、高校などで「8割ルール」などといって、
原稿用紙の8分目まで埋めれば減点されないと教わったことがあるかもしれません。
しかし、「8割埋めれば減点されない」は大ウソです。
できる限り、指定の文字数ピッタリに近づけるように回答しましょう。
また、文字数指定には次の3つの場合もあります。
「〜字以内」
「〜未満」
「〜程度」
受験生からよくある質問されるのですが、「〜程度」の場合、誤差が許されるのはどの範囲でしょうか?
具体的には次の通りです。
1,000字未満の場合、「+−50」
1,000字以上の場合、「+−100」
KOSKOSUでは、これを「1,000字ルール」と呼んでいます。
例えば、「800字程度で書きなさい」という指定があれば、750〜850字で答案を書き上げます。
また、「1,000字程度で書きなさい」という指定があれば、900〜1,100字で答案を書き上げます。
ちなみに、「800字以内」の場合、749字でも減点はされないでしょうが(+−50字はあくまでも目安)、
801字は「以内」という制約を超えてしまっているので減点対象になります。
これが「800字未満」の場合、799字まではセーフ、800字はアウトになります。
たかが1文字。
されど1文字。
たった1文字で天国と地獄にわかれます。
字数指定は厳守してください。
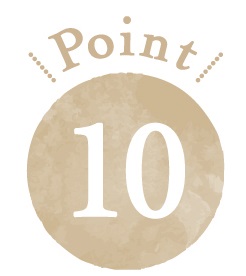
作法⑩シャープペンではなく、「鉛筆」で書く
小論文は鉛筆で書くのが基本です。
言うまでもありませんが、色ペンやラインマーカーは使ってはいけません。
小論文はあくまでも「文章」で評価されるものであって、目を引くビジュアルで評価されるものではないからです。
また、正式な文書はペンで書くのが基本ですが、
小論文の場合、試験中に書き上げる書類ですので、ペンで書いてしまうと修正ができません。
実際、一度も書き直しをしないで答案を完成させることはできないでしょう。
また、シャープペンで書こうとする受験生がいますが、おすすめできません。
私が鉛筆で書くことを推奨する理由は、強く素早く書けるからです。
シャープペンの場合、鉛筆と比べて芯が細いため、書いている途中で何度も折れてしまいやすいです。
その他にも私が鉛筆で書くことをおすすめする理由があります。
それは採点官があなたの小論文をコピーして読むからです。
採点時には決まって複数の採点官が同時に小論文を読みます。
そのためにも、コピーをして目を通すのです。
コピーをすると、自筆よりも薄くなってしまうことがあります。
昨今のコピー機は性能が上がったとはいえ、筆圧が弱いと、コピーに反映されないこともあるでしょう。
字が薄いと読みづらくなると同時に、印象も薄くなります。
その点、鉛筆なら比較的濃く書くことができます。
鉛筆のベストな濃さは「HB」もしくは「B」です。
試験当日だけ使おうとすると、うまくいきません。
ぜひ、日頃から慣れておいてください。
そして、当日は予備として5〜6本の鉛筆を持って行くことをお忘れなく。
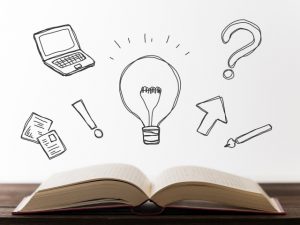
もし、今回の記事を読んで質問や相談がある方は、ぜひKOSKOS公式ホームページまでお問合せください。
また、KOSKOSではAO入試、推薦入試受験生、保護者を対象に無料個別相談を実施しています。
KOSKOSの認定講師がマンツーマンであなたの質問、相談にお答えします。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
質問、相談大歓迎!
